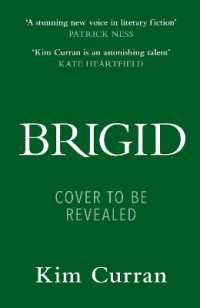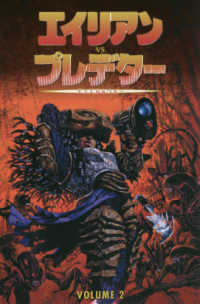内容説明
ただキレイなだけの美文は要らない。説得こそは文章の命だ。百学の思想家が伝授する「読み手を説得する」技術。
目次
第1章 説得力のある文章を書くための20カ条(最初の一文で魅きつける;繰り返し主語を書く;情報を一文に詰め込まない=文章は短文に切って連ねて書く ほか)
第2章 やってはいけない書き方10カ条(主語を省かない;あいまい表現を使わない;「という」を極力使わない ほか)
第3章 書く材料をどう取り扱うか(実感で分かることで人を説得する;「縫い合わせ」の大切さ;「幹+枝葉」 ほか)
著者等紹介
副島隆彦[ソエジマタカヒコ]
評論家。副島国家戦略研究所(SNSI)主宰。1953年、福岡県生まれ。早稲田大学法学部卒業。外資系銀行員、予備校講師、常葉学園大学教授等を歴任。政治思想、法制度、金融・経済、社会時事、歴史、英語研究、映画評論の分野で執筆・講演活動を続ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おおにし
19
副島さんの文章は大変クセがあるが、決して分かりにくい文章ではない。説得力のある文章の背景には、この本に書かれているようなルールによる徹底的な推敲があるのであろう。しかし、一番大切なのは、書いた本人が肝(はら)の底から分かって実感したことを書くことにある。「実感でわかったこと」でしか人を説得することはできない。これこそプロの言論人の言葉であると感じた。2020/01/26
はる
4
なるほど、副島氏の本に、どうして引き込まれてしまうのかと思ったら、そうだったのだと、まさしく納得する内容でした。読み手を説得するためにはどう書くべきかが、わかりやすくまとめられています。とくに第2章のやってはいけない書き方は勉強になります。理解しずらい本は、この「やってはいけない」ことをやってしまっているのだと実感させられました。今後、自分の作文時に、参考にしたいと思いました。2014/01/07
R Suzuki
3
決めつけや思い込みばかりと毛嫌いする人の多いことは百も承知だが、この副島隆彦による文章読本はかなり面白い。副島節といわれる独特な文体は説得の技術として意図的なものだと誰もが納得するだろう。気の毒なことに石原慎太郎や大江健三郎の文章が悪文の見本として文意を変えずに朱筆を加えられている。ヒロシマ・ノートが痛快副島節で生まれ変わるとどうなるか?奇跡のコラボか?いや、あいまいなもの言いは許さない、わかりやすく書け!という筆誅である。同様にダメだしされた宮台真司は何と言うだろう?人はなかなか説得には応じないからね。2014/01/08
ばしこ♪
2
文章を伝えるツールが多様化する現代で意識するポイントが多数ある。断言する。単純化する。主語を省かない。色々と具体的なことは本を実際に読んでいただければよいが、個人的に一番伝わったのは自分で書いた文章に誇りを持つこと。名前を堂々と掲示することで逃げ道をつくらないこと。このポイントは文章を書く以外でも使える。責任転嫁が蔓延っている今にカツを入れているのかもしれない。2014/04/13
Ich_co
2
「苦手だと思ったらすぐ閉じていいから!」という謎の文句とともに先輩が薦めてくれた一冊。確かに著者のクセが凄い!文章術を説くフリをしながら、言葉で飯を食う人の本気がこもってます。美文じゃなくて、「説得する」文章術。普通の文章術ではNGとされる表現もガンガンつかう。現役の著者達をガンガンdisる。こんな変なハウツー本は久しぶりだ。毒のない食パンのような文章を書けと教わって育った私には、真逆のアプローチが大変勉強になりました。ちょっとやってみよう。2013/12/22
-
- 洋書
- Brigid